 飼育環境や食事、獣医療の進歩などから昔と比べて犬の平均寿命は大きく伸びました。
飼育環境や食事、獣医療の進歩などから昔と比べて犬の平均寿命は大きく伸びました。
平均寿命が伸びたことで、昔ではあまり見られなかった「認知症」の犬も増えました。
今回は犬の「認知症」についてお話しします。
Contents
犬の「認知症」とは
犬の「認知症」は脳の老化などにより、今まで出来ていたことが出来なくなったり、
異常な行動を起こしたりする症状を言います。
一般的に11歳位から認知症の症状が見られることがあり、
15歳以上の犬では程度の差はあれ、多くの犬に見られます。
(※大型犬は平均寿命が小型~中型よりも短いため、
認知症の発症時期が上記の年齢より早いことがあります)
認知症はどんな犬種でも見られますが、
日本犬(特に柴犬)に多く見られるというデータがあります。
犬が認知症になる主な原因は加齢による「脳の変化」や
「神経伝達物質の減少」と考えられています。
犬の「認知症」の症状や行動
犬が認知症になると下記の症状や行動が見られることがあります。
- 同じところをグルグル旋回する
- 夜鳴きをする
- 排泄の失敗をする
- 食事を過剰に欲しがる
- 狭い場所に入り込む
- 壁にぶつかったまま戻れなくなる
- 呼んでも反応がない(※飼い主を認識しない)
- 今まで出来ていたことが出来なくなる
- 単調な声でずっと鳴き続ける
- 生活時間が昼夜逆転する
- 突然唸ったり噛むようになる
一般的に高齢犬にこれらの症状や行動が見られた場合は、
認知症の可能性があります。
ただし「トイレの失敗」や「呼んでも反応がない」などは
排泄器官の衰えや聴覚の衰えなど、認知症とは別の老化現象が原因ということもあります。
また、これらの症状が見られる別の病気の可能性もありますので、
認知症か、別の病気なのかを調べる意味でも獣医さんに一度相談しましょう。
犬の「認知症」の治療方法
認知症の治療は完治を目指すのではなく「現状維持」のための治療となります。
治療方法として行われているのは
- 薬物療法
- 食事療法
です。
夜鳴きや徘徊が酷い場合には、鎮静剤や安定剤を処方することがあります。
脳に良いと言われるDHAやEPAが含まれているフードや
血流を良くしたり、抗酸化作用のあるサプリメントを与える食事療法を行うと、
症状が緩和することがあります。
犬の「認知症」の予防方法
犬の認知症を完全に防ぐことは難しいですが、
認知症自体の予防や、認知症の進行抑制に下記の方法が効果的と考えられています。
散歩・頭を使う遊びやトレーニングを行う
犬の脳に刺激を与えることは、認知症の予防につながると考えられています。
散歩で色々な刺激を受けさせたり、おもちゃを隠して探させたり、
オスワリやマテなどのトレーニングをするなど…
日常で簡単にできる“刺激のあること”を行ってみましょう。
散歩コースは同じコースばかりではなく、
違うコースに行くと犬の刺激になります。
歩行が難しくなり散歩が出来なくなってしまった場合も
バギーで外に連れていくことで、
音やニオイなどの刺激を受けることが出来ます。
日光浴を行うなど昼夜逆転させないようにする
認知症になると昼に寝て夜に起き、徘徊や夜鳴きをすることがあります。
日中はしっかりと日光を浴び、刺激を与えて
夜に眠るという体内リズムを作ることが昼夜逆転の予防になりますので、
普段から心がけるようにしましょう。
まとめ
犬も高齢になると認知症になることがあります。
犬が認知症になり今まで出来ていたことが
出来なくなる様子を見るのはつらいですが、
犬もそんな体の不自由さにもどかしさを感じています。
犬の気持ちや様子を上手く読み取って、サポートをしていきましょう。
また、認知症の予防は脳への刺激が効果的と考えられています。
頭を使った遊びやお散歩など、脳に程よい刺激を与えるようにしましょう!








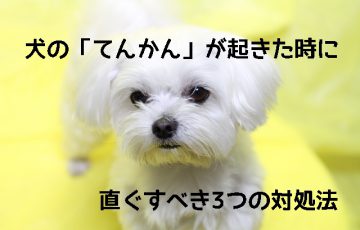

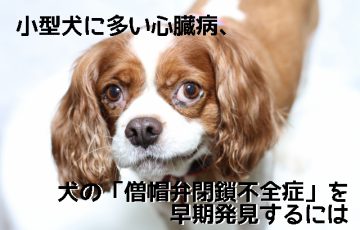

最近のコメント