 ネコちゃんは泌尿器の病気にかかりやすいのですが、
ネコちゃんは泌尿器の病気にかかりやすいのですが、
その中でも5匹に1匹の確率で発症しているのが「尿路結石」です。
尿路結石は若くても発症する病気ですが、飼い主さんが注意することで予防ができます。
また、治療後の「再発」防止も必要となります。
猫の尿路結石を予防するためにはどのような事をしてあげればよいのでしょうか?
Contents
猫の尿路結石を予防するために出来る4つのこと
- 水を多く飲ませる
- 排泄を我慢させない
- 食事のバランスに気を付ける
- ストレスを与えない
水を多く飲ませる
尿に結石が出来る原因の一つに、水分摂取量が少ないことで
尿が凝縮し、結石ができやすい状態になることがあげられます。
特に猫は砂漠出身であまり水を飲まず、
濃い尿を出すため、尿トラブルが起きやすいのです。
そのため普段の食事と共にたっぷり水分を取らせると
1日の水分摂取量を増やすことが出来ます。
普通にお皿に置いたままだとなかなか飲まない場合は
水分量の多いウェットフードを追加したり、
普段の食事での水分量を意識しましょう。
飲み水も一か所ではなく複数の場所に置いたり、
猫の好きな場所(高い場所、暗い場所など)に置いてみましょう。
流れる水を好む子にはウォーターファウンテンもおすすめです。
排泄を我慢させない
排泄を我慢させることも尿が凝縮してしまう原因の一つのため、
排泄の時間を多くとったり、
いつでも排泄できるようにトイレの掃除は小まめに行いましょう。
食事のバランスに気を付ける
ミネラルのバランスが不適切な食事は結石を作りやすくなります。
バランスの良い良質なフードを与えるようにしましょう。
フードの質は体質そのものに繋がります。
その点からも普段の食事には気を付ける必要があります。
ストレスを与えない
ストレスは泌尿器トラブルにも密に関係しているとされます。
騒音、寒さや暑さなどの飼育環境や
生活環境(引越し、外出など)の変化は猫へのストレスになります。
狭い場所や高い場所など落ち着ける場所を作り、
少しでも快適に過ごせるような工夫をしてあげましょう。
続いては尿路結石について詳しくお話しします。
猫の尿路結石の症状
- 頻繁にトイレに行く
- トイレの時間が長くなる
- トイレで動かなくなる
- 血尿
- 尿がキラキラする(結晶・結石の排出)
- お腹を触ると痛がる
尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に結石が出来ることにより、
物理的に炎症を起こしたり、結石が詰まることで、
排尿困難を引き起こします。
尿路結石が原因で膀胱炎を引き起こすこともあります。
頻繁にトイレに行くのに尿が出ないなどの症状があれば、
まず膀胱炎や尿路結石を疑います。
進行すると
- 排尿困難
- 尿毒症
- 膀胱破裂
などが起きます。
尿が出なくなってしまう尿毒症は、命の危険もあります。
いつもと様子が違うと感じたらすぐに病院に行きましょう。
猫の尿路結石の種類
猫がなりやすい尿路結石は下記の2種類と言われます。
- ストルバイト結石
- シュウ酸カルシウム結石
尿のph値がアルカリに傾くか酸性に傾くかにより結石の種類が変わります。
尿道が細くカーブをしているオス猫の方がメス猫よりも結石になりやすく、
年齢に関係なく発症します。
成猫期に多いのがストルバイト結石で、
老猫期に多いのはシュウ酸カルシウム結石です。
これらは結晶化しやすいpH値が異なるためコントロールの仕方も変わります。
また親猫が尿結石になっていると、子猫もなりやすい傾向にあります。
猫の尿路結石の治療法
- 外科手術
- 内科治療
まずは結石の有無を調べ、結石の大きさや数などから
外科手術を行うか判断しますが、多くは内科治療となります。
内科治療は薬と療法食での治療となります。
一度結石になると再発しやすいため、
永続的に療法食を与えるのが一般的です。
ストルバイト結石の多くは食事療法で溶かすことができますが、
シュウ酸カルシウム結石の場合は食事療法では効果が少なく、
結石が見つかった時点で手術になる事が一般的です。
いずれの結石の場合も「結晶」の段階であれば
外科手術にはならず、療法食やサプリメントでの処置となります。
最近では手作り食などで栄養バランスや水分コントロールを行う
飼い主さんもいます。
手作り食にする場合は適切な素材を与える必要があるので
獣医さんと相談をしましょう。
まとめ
ネコちゃんは元々泌尿器の病気になりやすい動物ですので、
日頃から尿に異常がないか意識しましょう。
水分摂取をしっかり行うことは結石のみだけでなく、
他の泌尿器系の病気の予防に繋がりますので
意識するように心がけましょう!
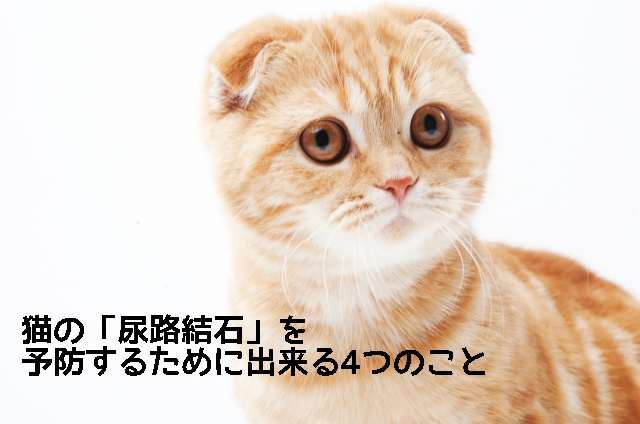











最近のコメント