 犬や猫に寄生する外部寄生虫の中で、怖い感染症を媒介するのが「マダニ」です。
犬や猫に寄生する外部寄生虫の中で、怖い感染症を媒介するのが「マダニ」です。
マダニは犬猫以外にも人間に寄生し、感染症を引き起こすことがあるですが、近年では死に至ることもある感染症が確認されたため話題となりました。
今回は「マダニ」とは一体どんな外部寄生虫なのかお話しします。
Contents
犬猫に寄生する「マダニ」とは
一般的に「ダニ」と呼ばれる布団などに生息する極小のダニとは異なり、
「マダニ」は大型のダニです。
成虫で3~8mm吸血をすると10倍まで膨れ上がるので肉眼で見ることができます。
マダニは昆虫ではなくクモの仲間で、足が8本あります。
マダニは草むらなどに生息し、動物の体に飛び移り寄生を開始するため、
散歩中の犬や、室外にいる猫に多く寄生します。
マダニが媒介して犬や猫に発症する病気は?
マダニが犬や猫に寄生すると下記の病気になることがあります。
犬
- 貧血
- アレルギー性皮膚炎
- ダニ麻痺症
- 犬バベシア症
猫
- 貧血
- アレルギー性皮膚炎
- 猫ヘモプラズマ症
マダニに吸血されたことで直接的に貧血を起こしたり、
アレルギー症状を起こして皮膚炎を起こすことがあります。
ダニ麻痺症はダニの唾液に含まれる神経毒により
筋肉が麻痺してしまう犬の病気ですが、日本ではあまり見られず
アメリカやオーストラリアで多く見られます。
マダニによる特に怖い犬の病気は「犬バベシア症」です。
マダニによって運び込まれたバベシア原虫が
赤血球を破壊し、貧血、発熱、食欲不振などの症状を引き起こし
急性の場合は死に至ることもあります。
猫の「猫ヘモプラズマ症」はヘモプラズマというリケッチア(微生物)が
マダニにより運び込まれ、貧血、発熱、元気消失、関節炎などを起こします。
マダニが媒介して人に発症する病気は?
マダニは人にも寄生し、様々な病気を引き起こします。
草むらや山林などを歩いた際に、
そのままマダニが寄生することもありますが、
犬や猫に寄生したマダニが飼い主に寄生することがあり、
犬や猫を飼っている場合は特に注意が必要とされます。
人がマダニに寄生されると
- ライム病
- 日本紅斑熱
- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
などの病気を発症することがあります。
中でも近年問題視されているのが
重症熱性血小板減少症候群
(じゅうしょうねっせいけっしょうばんげんしょうしょうこうぐん)【以下SFTS】です。
人がSFTSに感染すると消化器症状や倦怠感、リンパ節の腫れ、
出血症状などが見られ、死亡することもあります。
SFTSはSFTSウイルスを持ったマダニに吸血されることで発症します。
2009年に中国で初めて報告され、日本でも2013年に死者が出ました。
犬猫の場合は発症しないと考えられていたのですが、
2017年4月に猫、2017年6月に犬が人と同じような症状を発症しました。
その後はSFTSの症状が見られた動物からの咬傷、または濃厚接触で
人に感染したという事例があります。
犬猫の「マダニ」の予防方法
- 駆虫薬
- ボディチェックやブラッシング
- 服を着せる
マダニは駆虫薬によって予防することができますので、
マダニが増えだす春先から秋頃まで駆虫薬を使用することが
一番の予防方法となります。
マダニが皮膚に食いついてから、病原菌が体内に入るまでは
ある程度の時間が必要と言われています。
駆虫薬を使用していると、寄生自体は予防できないのですが
マダニが犬猫に付いても数時間後に駆虫されます。
駆虫薬は皮膚に直接垂らすスポットタイプと経口薬があります。
獣医さんに相談しましょう。
散歩の後にはマダニが付いていないか、
全身チェックとブラッシングをするようにしましょう。
マダニは皮膚に食いつくため、犬の散歩時に服を着せることは
マダニの寄生予防になります。
飼い主さんも同様に草木の多い場所では、
腕や足など露出しない服を着るようにしましょう。
犬猫が「マダニ」に寄生されたら
マダニが犬や猫に寄生しているのを見つけた場合は、
無理に皮膚から剥がそうとせず、動物病院へ行きましょう。
マダニを無理に剥がそうとすると、
マダニの口だけ皮膚に残ってしまい、
体内に病原菌が残ってしまう恐れがあります。
また、潰してしまうと病原菌が飛び散る可能性もあるため、
慎重に駆除する必要があります。
専用のピンセットがあれば家でマダニを皮膚から剥がすこともできますが、
慣れていないと難しいので、基本的には動物病院で駆除してもらいましょう。
まとめ
マダニは犬や猫だけでなく人にも寄生し、
感染症を引き起こす可能性があります。
定期的な駆虫薬での予防や、散歩後のボディチェックを徹底し、
マダニを見つけたら動物病院へ行くようにしてください。




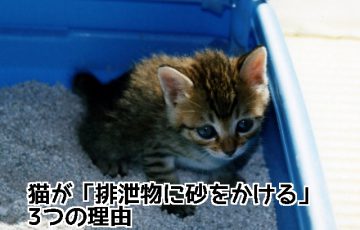







最近のコメント