 混合ワクチンや抗生剤の注射など、猫に「注射」をする機会は猫を飼育していると必ずありますね。
混合ワクチンや抗生剤の注射など、猫に「注射」をする機会は猫を飼育していると必ずありますね。
しかし、猫はこの注射が原因で「注射部位肉腫」という症状を稀に発症してしまうことがあります。
病気予防のために接種した注射が原因で病気になってしまうのは、なんだか怖いですが、知識としてしっかり覚えておくようにしましょう。
Contents
猫の「注射部位肉腫」とは
猫の「注射部位肉腫(ちゅうしゃぶいにくしゅ)」はワクチンや
その他の注射を接種した部位が肉腫化(ガン化)してしまう病気です。
注射部位肉腫は悪性度が非常に高く、再発率も高い治療の難しいガンです。
基本的には猫に発症し、犬など猫以外の動物ではほとんど発症しません。
注射を打ってから肉腫が発症するまでの期間は4週間から10年と幅があるため、
原因の特定は非常に困難です。
注射部位肉腫の好発部位は肩甲骨の間、肩甲骨の上後ろ足、脇腹、お尻などです。
注射部位肉腫を起こす原因はワクチン内に含まれる
「アジュバント(ワクチンの効果を高める成分)」や、
「白血病ワクチン」「ウイルス」など色々と考えられていますが、
確証には至っていません。
発症年齢は平均10才でピークは6~7才、10~11才です。
発症する確率は1~2/10,000匹程とされます。
猫の「注射部位肉腫」の症状
注射部位肉腫の一般的な症状として、
ワクチン接種後3ヶ月間~3年かけてシコリが徐々に大きくなります。
シコリが神経を圧迫したり、リンパや肺に転移することがあります。
ワクチンを接種した場所がシコリになることは一般的によくあり、
この場合は1ヶ月~3ヶ月ほどで自然に消失します。
しかし、徐々に大きくなり、消失しない場合は注射部位肉腫の可能性がありますので、
獣医さんに相談しましょう。
猫の「注射部位肉腫」の治療方法
- 外科手術
- 化学療法(抗がん剤)
- 放射線療法
注射部位肉腫は浸潤性が高い腫瘍(他の組織に根を張るような腫瘍)であるため、
外科手術で広範囲を切除する必要があり、
四肢に発生した場合は断脚が推奨されます。
切除しても肺への転移や、再発率も高いため、
化学療法や放射線療法も補助療法として行うことがあります。
猫の「注射部位肉腫」の予防方法
猫の注射部位肉腫は発症原因が不明なこともあり、
予防は難しいですが、下記の方法は発症のリスクを下げる効果が期待できます。
ワクチンの接種部位に注意する
肩甲骨への発生が多いことや、肩甲骨に肉腫が発生した場合
切除が難しくなることから、近年では両前脚や尻尾など
肩甲骨以外への注射接種が推奨されています。
また、同じ部位への注射を避けることも、発症リスクを下げると考えられています。
ワクチンの接種を控える
ワクチンは感染症から猫を守るためには必要不可欠なものです。
しかし、あくまで飼い主さんの選択となりますが
猫の飼育環境が下記の場合はワクチン接種を控えるという
選択をすることもできます。
- 完全室内飼育
- 多頭飼育ではない
- ペットホテルなどを利用しない
人間が家に病原菌を持ち込むこともあるため、
感染の可能性はゼロにはなりませんが、
他の猫との接触がないため、感染症のリスクは低くなります。
どちらを選択するか、ご家庭内でもよく話し合ってみましょう。
まとめ
猫の「注射部位肉腫」は注射がきっかけで起こることがあります。
しかし、注射接種後必ず起こる物ではありません。
注射接種後に肉腫になる可能性があることを知っておくと、
すぐに獣医さんに相談することができます。
注射接種は発症リスクの高い肩甲骨以外にしてもらい、
注射接種後は患部をよくチェックするようにしましょう。
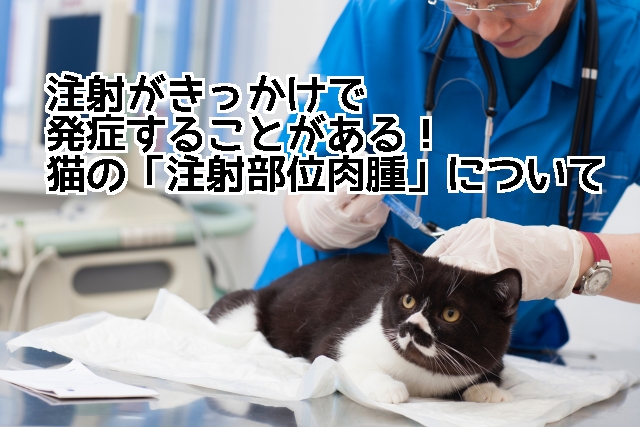



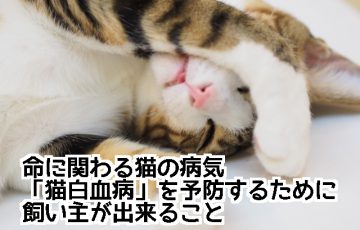


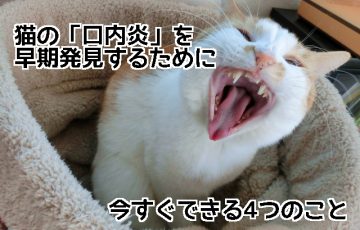




最近のコメント