 犬の「水頭症」という病気はご存知でしょうか?
犬の「水頭症」という病気はご存知でしょうか?
水頭症はその名の通り頭の中に水が溜まってしまう病気なのですが、近年流行の小型犬種によく見られます。
今回はこの「水頭症」について詳しくお話していきます。
犬の「水頭症」とは
犬の「水頭症」は、脳の内部を循環している「脳脊髄液(のうせきずいえき)」が過剰に分泌され
脳圧が高まることによって発生する病気です。
脳と脊髄は、硬膜、くも膜、軟膜という3層の「髄膜(ずいまく)」という膜で覆われています。
脳の中には脳室という空間があり、脊髄の中心にある脊髄中心管へ繋がっています。
髄膜の間と脳室、脊髄中心管の中は「脳脊髄液」という液体で
満たされていて、脳脊髄液により脳と脊髄は保護されています。
脳脊髄液は脊髄のくも膜下で作られて、髄膜と接する静脈から
血管の中へと流れていきます。
この脳脊髄液の流れがせき止められたり、
必要以上に増加すると脳が圧迫されて水頭症が発症します。
犬の水頭症は、奇形や出生前のウイルス感染などが原因の先天性水頭症、
頭部の外傷や脳炎、脳腫瘍などが原因で起こる後天性水頭症があります。
犬の「水頭症」の症状
- 落ち着きがない
- しつけ困難
- 不活発(ぼーっとするなど)
- 旋回運動
- 歩様の異常
- てんかん発作
- 視覚障害
- 全身まひ
- 昏睡状態
水頭症の症状は脳障害の症状であり、知能や行動に異常が見られます。
水頭症の犬の外見特徴として、
丸いドーム型の頭に両目の斜視が認められることがあります。
犬の「水頭症」になりやすい犬種
犬は先天的な水頭症が多く見られるのですが、
- チワワ
- マルチーズ
- ポメラニアン
- パグ
- ペキニーズ
- ミニチュアダックスフンド
などの小型犬種や、短頭種に特に多く見られます。
先天性水頭症の場合は生後2~3ヶ月で症状が見られるようになり、
1歳ごろまでには診断されます。
後天的な水頭症は、脳腫瘍や事故による外傷、ウイルス感染、
炎症などにより発生するため、
どの犬種でも発症する可能性があります。
しかし、成犬になっても泉門の閉じないことが多い
チワワなどの頭が丸いドーム型の犬は、
他の犬と比べて脳への外傷が起きやすく、
その点で、後天的な水頭症になりやすいと言えます。
犬の「水頭症」の治療方法
犬の水頭症はまず、典型的な症状から推測されることが多いですが、
CTやMRIを使用し、頭蓋内の構造を断層で観察して診断をします。
犬の水頭症は完治が難しい病気ですので、
症状の緩和を目的とした治療が行われます。
犬の水頭症の治療方法は
- 内科的治療
- 外科的治療
の二つがあり、主に内科的治療が多く行われます。
内科的治療は脳圧降下薬を用いて脳脊髄液の産生を抑え、脳内の圧力を低下させます。
外科的治療は、脳室内に溜まった脳脊髄液を腹腔へ流すためのチューブを設置する
「脳室-腹腔シャント術」という手術が行われます。
内科的治療で効果が見られない場合でも、
外科的治療を施すことで症状が改善することがあります。
後天的な水頭症で他の病気が原因になっている場合は、その病気の治療も行います。
脳脊髄液は常に作られているため、早期に治療を開始することが
脳へのダメージを最小限に抑えるための最善策です。
犬の「水頭症」の予防方法
先天的な水頭症の予防方法はありませんが、
後天的な水頭症は、原因の一つである「脳への外傷」を
飼い主さんが日常で気を付けることで予防ができます。
そのためにも、
- 高いところからの落下
- 犬を抱っこして落としてしまう
- 頭を叩く
などをしないように気を付けましょう。
まとめ
犬の「水頭症」は一度発症すると完治が難しく、
生涯付き合わなくてはいけない病気です。
早期の治療を始めるためにも、愛犬の行動に少しでも異常が見られたら
病院に行くようにしましょう。



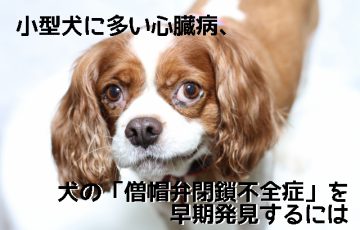
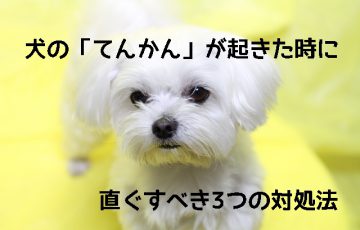







最近のコメント