 猫に寄生する厄介な寄生虫の一つである「ノミ」。
猫に寄生する厄介な寄生虫の一つである「ノミ」。
このノミが原因で起こる猫のアレルギー症状として「ノミアレルギー性皮膚炎」があります。
今回は猫の「ノミアレルギー性皮膚炎」について詳しくお話しします。
Contents
猫のノミアレルギー性皮膚炎とは
猫の「ノミアレルギー性皮膚炎」は
ノミ(主にネコノミ)に噛まれることが原因で起こるアレルギー反応の一種です。
ノミに噛まれるとノミの唾液が体内に侵入しますが、
この唾液中にあるタンパク質がアレルゲンとなり、
アレルギー反応を引き起こすと言われています。
初めてノミに噛まれた際には発症せず、抗体ができた二度目から
アレルギー反応が起き、酷い痒みに襲われます。
また、人もノミに噛まれることで皮膚炎になることがあります。
猫のノミアレルギー性皮膚炎の原因「ノミ」について
「ノミ」は昆虫類で体長2~3mm、
第3脚がよく発達し、跳躍に適した構造になっています。
オスもメスも成虫のみ吸血をします。
猫に限らず、犬、人、フェレットなど哺乳類であれば何でも吸血します。
夏から秋(気温約20~30℃、湿度約70%)にかけて最も活発になります。
ノミは卵→幼虫→蛹→成虫と完全変態を行う昆虫で、
一度成虫が猫に寄生すると卵や幼虫、蛹も猫の飼育環境に潜んでしまいます。
ノミはペストなど人間にも感染する病原体を媒介し、
猫にとってはで瓜実条虫(寄生虫の一種)の中間宿主でもあります。
猫のノミアレルギー性皮膚炎の症状
- 皮膚の炎症
- 脱毛
- 強いかゆみを伴う丘疹(きゅうしん)
- 急性湿疹
- 紅斑(こうはん)
これらの症状が背筋に沿って首や腰の部位に現れることが多いです。
腰や腹部は舐めることによって脱毛が進みます。
ノミアレルギーは寄生するノミの数が少数でも重症になることがあり、
寄生数が症状の重症度に直接起因しないことがあります。
猫のノミアレルギーの治療方法
まず皮膚病の発生部位や病変の所見、ノミの発生する時期かどうか、
体に黒いノミのフンが付着していないかを観察し、診断していきます。
猫のノミアレルギー性皮膚炎は、主に下記の治療方法が行われます。
- ステロイド(副腎皮質ホルモンの投与)
- 抗生物質の投与
- ノミ駆除剤の使用
痒みが非常に強い場合はステロイドを投与することで改善します。
痒みによる引っかきなどで患部が二次感染を起こしている場合は、
抗生物質の投与を行います。
また、原因となっているノミの駆除を行うためにノミ駆除剤も使用します。
猫のノミアレルギー性皮膚炎の予防
- 室内飼育にする
- 人によるノミの持ち込みに注意する
- ノミの駆虫薬を使用する
- 掃除を行い清潔にする
室内飼育にする
ノミは屋外の草むらや縁の下など、猫が好む場所に潜んでいます。
そこでノミに寄生され、室内に持ち込んでしまうと大変厄介です。
猫は室外には出さずに、室内飼育を心がけるようにしましょう。
人によるノミの持ち込みに注意する
人は外出しますので、気付かないうちにノミを室内に持ち込んでしまうこともあります。
ノミのいそうな場所(草むらなど)に行く際は虫よけスプレーの使用をしましょう。
また、野良猫はノミに寄生されていることがあるので、近寄る際は気を付けましょう。
ノミの駆虫薬を使用する
ノミの駆虫薬を定期的に使用しましょう。
駆虫薬の種類によってはノミの成虫を駆除し、
さらに卵の発育を阻害することができます。
飼育環境にノミが一度入り込んでしまった場合は、
ノミを一旦駆除しても、同一の環境下で猫を飼育している限り
再びノミの寄生を受ける確率が高いです。
しかし、駆虫薬は残存するため、再度の寄生防止・駆除もできます。
多頭飼育の場合は、他の猫にも寄生している可能性があるため、
すべての猫に駆虫薬を使用しましょう。
駆虫薬を使用する際は獣医師に相談をし、処方をしてもらいましょう。
掃除を行い清潔にする
ノミは室内では部屋の四隅、家具の下や隙間などの
暗く湿った場所や、カーペットやベッドの下などに潜んでいます。
室内は暖かいため、生息されると一年中繁殖することもあります。
ノミの潜みやすい場所は常に清潔にし、
ノミ駆除剤の散布も行うと良いでしょう。
まとめ
猫のノミアレルギー性皮膚炎は一度発症すると皮膚に痒みや炎症が起きて、
猫にとってつらい症状ということが分かりました。
治療によって改善が見られやすい症状ですが、駆虫薬の使用や、
屋外のノミの生息域に近寄らないようにすることでノミの寄生を防げます。
ノミは繁殖力が非常に高いため、
家の中に入るとすべてを駆除するまでかなりの時間がかかってしまいます。
猫も人間も被害を受けますので、ぜひ予防を心がけるようにしましょう。






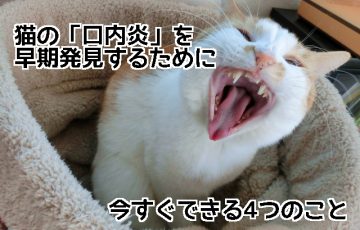

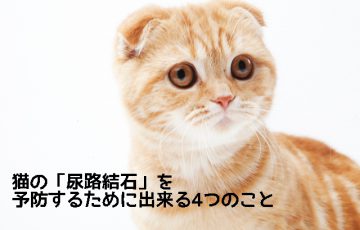



最近のコメント