 「猫鉤虫(こうちゅうしょう)」は猫の小腸に寄生する内部寄生虫ですが、寄生されると吸血され、様々な症状を引き起こします。
「猫鉤虫(こうちゅうしょう)」は猫の小腸に寄生する内部寄生虫ですが、寄生されると吸血され、様々な症状を引き起こします。
今回はこの「猫鉤虫」が引き起こす猫の「鉤虫症」についてお話しします。
Contents [hide]
猫の「鉤虫症」とは
猫の鉤虫症は猫鉤虫(以下鉤虫)という
8~20mmほどの白く長い寄生虫が、猫の小腸に寄生し、
吸血することで起きる症状を言います。
鉤虫が産卵すると、その卵は宿主である猫の糞便中に排出されます。
卵から孵化した幼虫は外界で発育し、感染能力を持つようになります。
この幼虫が経口感染したり、皮膚に穴をあけて経皮的に感染します。
また、母子感染(母猫の乳汁や胎盤を介する感染)することもあります。
猫の「鉤虫症」の症状
- 便の異常(下痢・血便・タール状便)
- 脱水症状
- 貧血
成猫の場合、少しの鉤虫に寄生されても無症状のことが多いですが、
寄生数が増えると下痢や血便などが見られ、
これに伴い脱水症状を起こすことがあります。
鉤虫は吸血するため、数多くの鉤虫に寄生された場合は貧血を起こします。
子猫の場合は成猫より重症化しやすく、
便の異常、脱水、貧血以外に発育不足などの症状が見られ、
症状が悪化すると死亡することもあります。
猫の「鉤虫症」の治療方法
- 駆虫薬の使用
- 点滴
ピランテルパモ酸塩やフェバンテル、
ミルベマイシンオキシムなどの駆虫薬を投与し、鉤虫を駆除します。
一度の駆虫薬ではすべての鉤虫を駆虫できないため、
獣医さんに指示された期間、しっかり飲ませる必要があります。
脱水症状が起きている場合は、点滴を行います。
猫の「鉤虫症」の予防方法
- 猫を室外に出さない
- 糞便検査を行う
- 糞便を早めに処理する
猫を室外に出さない
鉤虫症は野良猫など、不衛生な場所で生活する猫に多く見られます。
猫を室外に出している場合は、野良猫の糞便と接触することで
鉤虫症に感染する可能性があります。
室外飼育を心がけるようにしましょう。
糞便検査を行う
室外に出る機会のある猫は、定期的に糞便検査を行いましょう。
また、野良猫など衛生環境の悪い場所から保護した猫を飼う場合は
必ず糞便検査を行ってください。
糞便を早めに処理する
猫の糞便内の卵は、孵化するまでは感染能力を持ちません。
そのため、糞便を早く処理すれば寄生虫の蔓延を防ぐことができます。
猫の「鉤虫症」は人に感染する?
猫の鉤虫症は人も感染することがありますが、
幼虫が人の皮膚を穿孔して感染しても、
成虫まで発育することなく死滅します。
しかし、穿孔した皮膚とその周辺を幼虫が移行することで
皮膚炎を起こすことがあります。
まとめ
猫の鉤虫症は鉤虫が猫の小腸に寄生し、
吸血することにより起きる症状です。
成猫の場合、症状が軽いことがありますが、
放っておくと他の猫への感染源になってしまいます。
子猫の場合は重症化しやすいので、
嘔吐、下痢などの症状が見られたら動物病院へ行き、
糞便検査をするようにしましょう。






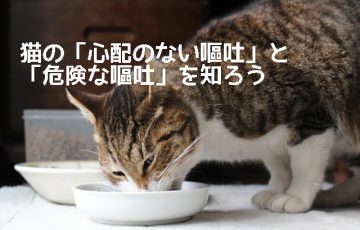

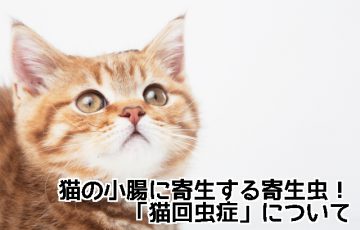

最近のコメント