 「犬ジステンパーウイルス感染症」(以下犬ジステンパー)は、特に免疫力の低い子犬や老犬が感染すると、命に関わることのある怖い病気です。
「犬ジステンパーウイルス感染症」(以下犬ジステンパー)は、特に免疫力の低い子犬や老犬が感染すると、命に関わることのある怖い病気です。
では、犬ジステンパーに感染しないようにするには一体どうすればいいのでしょうか?
Contents
犬ジステンパーの感染を防ぐためにできる3つのこと
犬ジステンパーの感染予防には下記の3つがとても重要となります。
- 子犬のワクチンプログラムを守る
- 年一回のワクチン接種を行う
- 感染源となる場所に近づかない
子犬のワクチンプログラムを守る
犬ジステンパーはワクチンで予防ができる病気のため、
ワクチン接種が第一に重要な予防方法となります。
子犬のワクチン接種の時期は成犬とは異なるタイミングで行う必要があり、
これを「子犬のワクチンプログラム」と言います。
子犬は母親の初乳から抗体を約95%もらうのですが、
成長と共にその抗体は徐々に失われていき、感染症にかかりやすくなります。
そのため、抗体が切れるタイミングでワクチン接種を行い、
新たな抗体を作る必要があります。
しかし、抗体が切れるタイミングには個体差があるため、
生後60日で1回目、1ヶ月後に2回目、さらに1ヶ月後に3回目というように
回数を分けてのワクチン接種を行う必要があります。
(ワクチンの回数や打つ時期は、獣医さんの考えによって多少異なります)
ワクチンプログラムが終わって抗体が付くまでの間は
他の犬との接触を避けることも、犬ジステンパーの感染予防に繋がります。
年1回のワクチン接種を行う
子犬のワクチンプログラム終了後は、
1年ごとのワクチン接種で犬ジステンパーを予防することができます。
年1回のワクチンの接種を欠かさないようにしましょう!
感染源となる場所に近づかない
犬ジステンパーは伝染性が非常に強く、
接触感染や飛沫感染をする病気のため、
狭い場所でたくさんの子犬が飼育されている
不衛生なペットショップなどで集団感染が起きることがあります。
そういった場所にワクチン未接種の犬や子犬を連れて行かないように注意しましょう。
犬ジステンパーとは
犬ジステンパーは犬ジステンパーウイルスに感染することで発症する感染症です。
人間の麻疹(はしか)に似たウイルスで、
イヌ科の動物に対して特に高い感染性がありますが、
ネコ科、イタチ科などほとんどの食肉目の動物に感染します。
感染ルートは「接触感染」と「飛沫感染」があります。
接触感染
すでに感染している犬の目ヤニ、鼻水、唾液、尿、便などに接触して感染
飛沫感染
すでに感染している犬の咳やくしゃみなどでのウイルス飛散による感染
免疫力の低い1歳未満の子犬でワクチン未接種、
ワクチンプログラムが終了していない場合に多く感染が見られます。
成犬は、高齢犬や他の病気で免疫力が下がっている場合に発症することがあります。
犬ジステンパーの症状
まず初期症状では
- 目ヤニ、鼻水
- 40度前後の発熱
- 食欲低下
- 元気消失
などが出ます。
続いて
- 咳
- くしゃみ
- 嘔吐
- 下痢
などの呼吸器症状、消化器症状が出ます。
さらに免疫力が低下していると、ウイルスが神経にまで達し、
- 脳脊髄炎
- マヒ
- けいれん
などの神経症状が出ることもあります。
その他にも網膜の異常や、肉球が角質化してしまうハードパットなどの症状が見られる事もあり、
症状が落ち着いても後遺症が残ることなどもあります。
病状は犬の体力・免疫力の状態によって変わりますが、
子犬や老犬の場合は重症化することが多く、死亡することもあります。
犬ジステンパーに感染した場合の治療方法
犬ジステンパーに感染した場合の特効薬というものはなく、
- 点滴
- 抗生物質
- 抗けいれん剤
などの対症療法のみとなります。
細菌による二次感染を防ぐための抗生物質、
神経症状のための抗けいれん剤などの対症療法を行いつつ、
点滴で栄養や水分補給を行い、犬自身の体力を高めることで
回復を目指します。
まとめ
「犬ジステンパー」は感染すると、死亡することもある怖い病気というだけでなく、
治療薬がなく、対症療法のみのため、「予防」が一番の対策となります。
犬ジステンパーを防ぐには、混合ワクチンの接種や
感染源となる場所に近づかないことが重要です。
ワクチン接種を正しい時期に行うことや、定期的に行うことで感染の予防や、
感染した場合も軽度な症状で回復することができます。
特に子犬や老犬など免疫力の低いわんちゃんの場合は、注意しましょう!

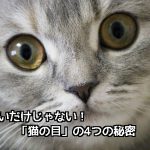










最近のコメント