 猫が発症する腫瘍の中でも「肥満細胞腫」は発症率が高く、発症した場所によっては様々な症状を引き起こし、死亡することもある怖い病気です。
猫が発症する腫瘍の中でも「肥満細胞腫」は発症率が高く、発症した場所によっては様々な症状を引き起こし、死亡することもある怖い病気です。
今回は猫の「肥満細胞腫」が、いったいどんな病気なのかについてお話しします。
猫の「肥満細胞腫」とは?
猫の「肥満細胞腫」は、「肥満」と付くので
一見すると肥満気味の猫がなる病気に見えますが、
実際は皮膚や粘膜に広く分布する「肥満細胞」に発生する「腫瘍」であり、
どんな猫でも発症の可能性があります。
好発年齢は中~高齢ですが、若齢でも発症し、
遺伝的にシャム猫に多く発生すると言われています。
肥満細胞腫は腫瘍ができる部位によって
「皮膚型肥満細胞腫」と「内臓型肥満細胞腫」に分けられます。
猫の「肥満細胞腫」の特徴
- 皮膚型の場合は比較的悪性度が低い
- 内臓型の場合は悪性度が高い
- 猫は犬に比べて内臓型が多い
「皮膚型肥満細胞腫」は比較的「悪性度が低い」と言われますが、
肥満細胞腫の形状や発生する部位により様々であるため、
見た目だけで悪性か良性かの診断をすることはできません。
そのため早期発見し、検査をすることがとても重要です。
「内臓型肥満細胞腫」は「悪性」の確率が高く転移もしやすいと言われます。
内臓型は皮膚型に比べて発症は少ないですが、
猫は犬と比べて内臓(脾臓、腸間膜、リンパ節)に肥満細胞腫が
発生する割合が多いことがわかっています。
一見すると皮膚型は良性が多く、問題がないように感じられますが、
見つかった皮膚型肥満細胞腫が内臓型肥満細胞腫から転移した可能性もあるため、
肥満細胞腫の疑いが見られたらすぐに病院へ行きましょう。
猫の「肥満細胞腫」の症状
皮膚型肥満細胞腫の主な症状は
- 頭や首の回りにシコリができる
- シコリができた部分の脱毛
- 腫れや出血
等が見られます。
1個だけポツリと体の一部にシコリができることが多いのですが、
多発することもあります。
また、肥満細胞は炎症反応を起こすヒスタミンなどを含んだ顆粒をたくさん持っているため、
急に腫れたり、出血することもあります。
内臓型肥満細胞腫の症状は
- 嘔吐
- 下痢
- 食欲不振
- 元気消失
- 体重減少
- 腹部がシコリで固くなる
等が見られます。
猫の肥満細胞腫の3つの治療方法
猫の肥満細胞腫の治療は、下記の三つの方法が主に行われます。
- 薬物療法
- 外科手術
- 放射線治療
まず、腫瘍が良性か悪性かは見た目で判断できないため、
細胞診などの検査を行います。
※正確な悪性度の検査は病理組織検査が必要
検査の結果から、薬物療法、外科手術、放射線治療などを
単独または併用して行います。
一般的に悪性度の高い内臓型は外科手術が原則とされ、
薬物療法や放射線治療は補助的に行います。
皮膚型の場合も基本的には外科手術による切除を行いますが、
自然に治ることもあるため、薬物療法を優先したり、経過観察することもあります。
肥満細胞腫が良性だった場合も、
再発の可能性が高いため継続的な観察や検診が必要です。
また、肥満細胞腫ができること=免疫力が低下している状態とも言えます。
治療の他に免疫力を高めるサプリメントなども使用し、
再発防止のためにも免疫力を高めるようにしましょう。
猫の「肥満細胞腫」を早期発見するには
- 毎日のボディチェック
- 嘔吐や下痢が長引く場合は病院へ
肥満細胞腫は皮膚にできた場合、
おできやシコリとして肉眼で確認することができます。
おできやシコリは肥満細胞腫なのか、良性なのか悪性なのか、
内臓型肥満細胞腫からの転移かはその時点ではわかりませんが、
飼い主さんが見つけやすい病気のサインの一つではあります。
皮膚におできやシコリがないかを確認するため、
毎日のボディチェックを行いましょう。
内臓型の場合は悪性度が高く、転移の可能性も高いため、
特に初期の対応が重要となります。
内臓型の症状の一つである「嘔吐」は
毛づくろいをする猫にとっては日常で比較的多く見られます。
そのため軽視しがちですが、
「嘔吐が長く続く」「下痢」「体重減少」などが見られる場合は
他の病気のサインの可能性がぐっと上がります。
早めに病院で見てもらうようにしましょう。
まとめ
皮膚にできたおできやシコリは問題がない場合もありますが、
悪性の肥満細胞腫など怖い病気のサインの可能性もあります。
放っておいても大丈夫な物なのか、悪い物なのかの判断は難しいため、
おできやシコリを見つけたらまずは病院に行きましょう。
毎日のボディチェックでは皮膚にできたおできやシコリの他、
腹部にできた固いシコリも早期に見つけることができます。
ぜひ、習慣的に行うようにしましょう。
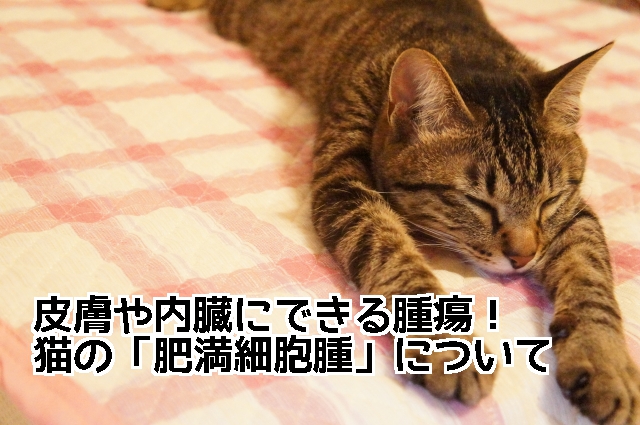






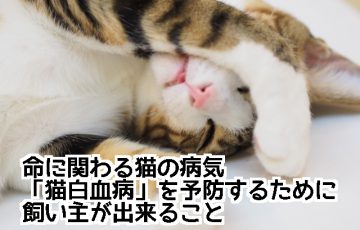
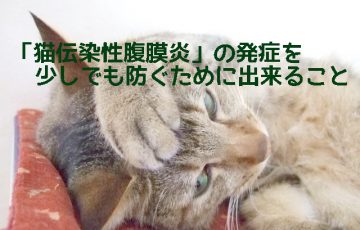
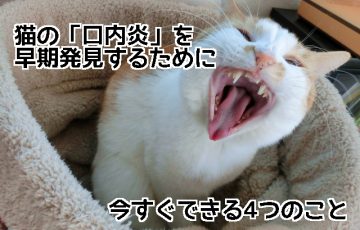


最近のコメント